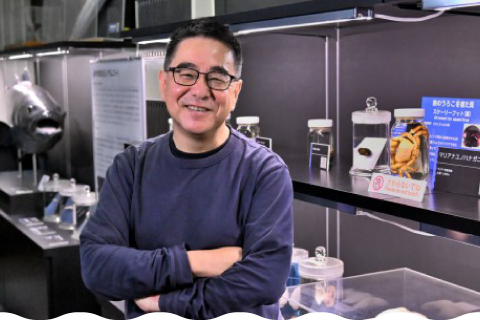
A.私は栃木県足利市で育ちました。近くに海がない環境でしたが、実家が鮮魚店を営み、父は釣り好きだったこともあり、次第に水の中の生き物に惹かれていきました。 高校生になり、進学先を決めるにあたって「自分が一番楽しいと感じることは何か」と改めて自分に問いかけたところ、思い浮かんだのが水の生き物と過ごす時間でした。 その思いから東京水産大学(現 東京海洋大学)へ進学しました。大学では淡水生物を研究していたため、当初、海の生き物については詳しく知りませんでしたが、大学院生の時にアルバイトとして参加したグリーンランド沖での深海水産資源調査が転機となりました。 想像以上に豊かで奥深い海の生態系に触れたとき、「海の生き物って、本当にすごい」と心から感じました。その感動が私の研究の方向性を大きく変え、今日までつながっています。
A.自分がやりたい仕事を考えたとき、最初から深海生物に携わりたいと思っていたわけではなく、とにかく「水の中の生き物と関わる仕事をしたい」という気持ちが強くありました。そんな中、大学の研究室に「海洋科学技術センター(現 海洋研究開発機構(JAMSTEC)の『しんかい2000』に乗って深海調査に行ってみないか」という話が舞い込みました。私は「深海に行けば何か新しい発見があるんじゃないか」という期待とロマンを抱き、深海生物に興味をひかれました。これが海洋研究開発機構(JAMSTEC)を意識するきっかけとなりました。

A.これまで深海生物研究に取り組んできました。それをベースにして携わってきた主な取り組みは3つあります。1つ目は、2000年から2010年にかけて日本の窓口として参加した国際プロジェクト「海洋生物のセンサス」です。世界中の海洋生物の過去・現在・未来を調査し、そのレガシーはOBIS (Ocean Biodiversity Information System) という海洋生物の多様性を網羅したデータベースとして、今も世界の海洋生物の多様性研究や海洋生物が関わる社会問題や政策提言の情報基盤となっています。2つ目は、東日本大震災後の漁業復興を目的にした「東北マリンサイエンス拠点形成事業」です。JAMSTECは漁業に直接関わった研究は少なかったものの、海洋研究のノウハウを駆使して、現場に役立つ情報提供に取り組みました。そして3つ目は、近年注目が高まる「海洋プラスチック問題への対応」です。JAMSTECではロボットを活用した深海調査を重ねてきましたが、調査のたびに海底に沈むごみの存在を目にしてきました。調査現場での経験も踏まえ、現在も海洋プラスチック問題に関する研究に取り組んでいます。
A.これまでで一番大変だった経験は、2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震後の深海調査です。地震直後、海の表面には無数の瓦礫が浮かび、船を自由に動かすことすら困難な状況で、実施できる調査は限られていました。「しんかい6500」による深海調査では海中の視界が重要なのですが、余震の影響で海中の濁りがなかなか収まらず、視界が悪い状態が続いていました。そうした極限の環境下での潜航は、正直なところ「怖さ」を感じました。通常は海底から2-3 mの高度で走りながら観察するのですが、突然のがけ崩れに対処するために、海底から4-5 mの高度で航走したり、搭載するおもりを少なくして万が一のときはすぐに海底から離れられるようにするなど、余震が続く中であらゆる対策を講じながら慎重に調査を進めていきました。


A.大きく3つあります。1つ目は「深海生物の多様性に関する研究」です。現在、生息している深海生物が、環境の変動によってどのように変化していくのかをテーマに研究を進めています。この研究では、環境DNA*や実際の生物を観察・採集しながら分析することで、深海生物の多様性や分布の変化を調べています。このなかには「海洋保護区の管理・モニタリング」も含まれます。SDGsの目標14や生物多様性条約では、「2020年までに海域の10%以上を海洋保護区など保全する海域として指定する」という目標が掲げられていますが、海洋保護区は単に設定するだけでは不十分であり、継続的な管理とモニタリングが不可欠です。 私たちは、日本の深海底に設定された海洋保護区で生物多様性の維持や環境の変化を把握するために、環境DNAの分析に加え、「しんかい6500」やロボット技術などを活用し、モニタリングを実施しています。2つ目は「海洋プラスチック問題の解明」です。現在、海に流出している膨大なプラスチックのうち、科学的に把握できている量は全体の10%程度に過ぎません。残る90%の“ミッシングプラスチック(行方不明プラスチック)”の行方を追跡するとともに、マイクロプラスチックの分析効率を高める技術開発にも取り組んでいます。3つ目が、「環境影響評価」です。人類は、海底資源の開発など海の利用を進めていますが、環境への影響が懸念されています。私たちは、開発が海の環境にどのような影響を及ぼすのかを知るための技術開発に取り組んでいます。
*環境DNA・・・様々な生物の糞や粘液などに由来する環境中に存在するDNAのかけら


A.これまで沖ノ鳥島や南鳥島周辺の海域を自ら調査した経験はありませんが、現時点でキンメダイ類やカツオ類が生息していることは確認されています。また、東京都の研究調査として、いであ株式会社が令和5年度に沖ノ鳥島周辺海域で実施した環境DNA調査において、ヨコヅナイワシが検出されました。深海に生息するヨコヅナイワシは、食物連鎖の頂点に位置する「トップ・プレデター」と呼ばれる生物です。トップ・プレデターが存在することで、他の生き物が増えすぎることなく、生態系のバランスが保たれるため、沖ノ鳥島周辺の深海は、健全な生態系が残っている海域であることを垣間見ることができました。

A.沖ノ鳥島・南鳥島に関しては東京都が研究調査を実施しているところですが、両島は本土から遠く、現時点で十分な調査・研究が行われているとは言い難い状況です。海洋生物の情報を蓄積するためにデータベースに情報を登録しようとしても、登録すべきデータを収集できていないため、生物の分布を正確に把握する調査が不可欠です。沖ノ鳥島や南鳥島周辺海域まで船を出すには多大な費用がかかるという課題もありますが、私たちは他の研究機関などが集めたデータもしっかりとデータベースに収納し、海洋生物研究、政策などに役立てて欲しいと考えています。



A.生物多様性や海洋プラスチックの問題は、まだ多くの人に十分伝わっていないと感じています。研究者は論文を出して終わりになりがちですが、本来はその成果が何を意味するのかを社会に広く伝えることが重要です。いわゆる「アウトリーチ活動(社会への情報発信)」です。例えば、海洋プラスチックの深刻さを知ることで、人々の行動が変わる可能性があります。世界の人々が、プラスチック製品のリサイクル活動などに積極的なのは、その例かと思います。科学的知見を、正確に、わかりやすく届けることが、今後ますます求められると感じています。
A.子どもの頃、私にとって海は、年に一度行けるかどうかの特別な場所で、貴重でワクワクする存在でした。しかし、現在、私たちは無意識のうちに海に頼りすぎており、過剰な負荷をかけてしまっていると感じています。このままでは、海からの恵みを受けられなくなるかもしれません。これからも海の恵みを受け続けるためには、科学的な知見をもとに海のおかれている状況を社会へ向けて発信し、海の利用と保全のバランスを考えることが大切だと思っています。

A.沖ノ鳥島や南鳥島は、日本の排他的経済水域(EEZ)を主張するうえで非常に重要な起点です。そして、起点の島として、より広く認めてもらうには、きちんとした管理が求められます。管理といってもさまざまですが、例えば、そこにどんな生き物がいて、環境がどう変化しているのかを把握することも、立派な管理の一つだと私は考えています。沖ノ鳥島や南鳥島は都心から遠く離れた位置にありますが、東京都の島ですので、都民の皆様に少しでもその意識を持っていただけたら嬉しいですね。そのために、私たちもできる限りの協力をしていきたいと思っています。