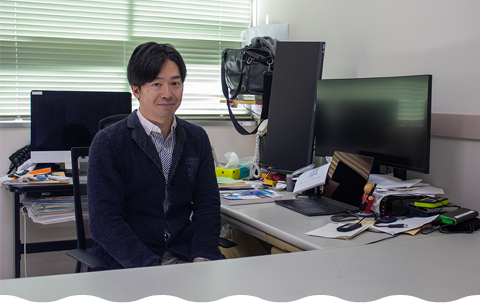
A.私は過去の地球環境と地質学に興味を持っており、大学では理学部地球科学科に入りました。卒業論文では、山口県秋吉台の石灰岩を対象に研究を行いました。それが私の研究の出発点です。大学院に進学後、さらに古い時代を研究したいと思い、約6億年前のエディアカラ紀の岩石と海洋に関する研究を行いました。その後、茨城県つくば市にある産業技術総合研究所に就職しました。そこで本格的に海洋地質の研究に取り組むようになり、2018(平成30)年からは海洋地質に関する縁で東京海洋大学に移りました。現在は、東京海洋大学で海洋地質に関する研究を行う一方、学生時代から続けている陸上の岩石を対象にした過去の海洋環境の研究にも取り組んでいます。
A.海洋地質学は、地質がどのように発達していったのかを海洋を舞台に研究する学問です。また、炭酸塩堆積学は、サンゴ礁を起源とする炭酸塩堆積物が、どのような場所で、どのようにたまっていくのかを研究します。炭酸塩堆積物がたまった場所の発達過程を考えるには、海洋地質に関する知識が欠かせず、2つの学問は密接に関わっています。
A.炭酸塩で形成される代表的な岩石である石灰岩は、過去のサンゴなどの生物が埋没して形成されており、そこには当時の海洋環境に関する情報が含まれます。私は高校時代から、そのような石灰岩を通して、過去の海洋環境や地球環境がどのような状況だったのかを研究することに興味を持っていました。大学進学にあたっては、研究を本格的に行えることはもちろん、大学時代ならではの経験ができる環境で学びたいと考えました。その結果、サンゴ礁で形成された島々が特徴の沖縄に惹かれ、琉球大学を選びました。沖縄は、炭酸塩堆積学を研究する上で非常に興味深いフィールドであり、現地での研究を通じて多くの発見や経験を得られたと感じています。

A.海洋地質学では、外洋と沿岸域の地質を対象に研究を行います。私は、自分が住む地域や研究フィールドがどのように形成されてきたのかを明らかにする点に強い関心があり、主に沿岸域を研究対象としています。沿岸域では、陸上の地質が海域まで連続しており、海域を調べることで陸上の地質形成や発達をより具体的かつ詳細に理解することができます。また、外洋における地質学的な研究も並行して行っており、具体的には、沖縄を含む琉球列島全体がどのように発達してきたかを解明するために、反射法音波探査を用いて海底下の地層を調べたりしています。この技術を使うことで、地質の発達過程の詳細な理解が可能となります。
一方、炭酸塩堆積学では、石灰岩や苦灰石といった炭酸塩岩を地層から採取し、当時の海洋環境について調べています。私が特に興味を持っているのは、エディアカラ紀と呼ばれる時代です。この時期は、生物が爆発的に進化する「カンブリア爆発」(約5億4,000万年前)の直前にあたります。カンブリア爆発では、脊索を持つ動物が急激に増加しましたが、なぜこのような進化が起きたのかを解明するには、その直前の時代であるエディアカラ紀海洋環境を調査することが重要です。

A.私が担当している講義では、主に海洋地質学とその研究手法について取り扱っており、データの収集や調査の方法などを学生に教えています。また、学部1・2年生を対象とした講義では、複数の教員が分担して地学全般に関する内容を担当し、私は、岩石の種類や砂や泥といった堆積粒子の堆積過程について教えています。講義を通して、学生たちが地質学の基本的な理解を深められるよう努めています。


A.東京都が沖ノ鳥島の研究調査を行っていることを知り、自分の研究テーマとして沖ノ鳥島を意識するようになりました。そこから沖ノ鳥島について調べる中で、これまでの研究フィールドである山口県秋吉台と沖ノ鳥島が共通した地質的特徴を持つことに気付き、沖ノ鳥島への関心がさらに高まったこともあり、公募に応募することを決意しました。
A.沖ノ鳥島およびその周辺海域における海底地形の特徴を明らかにすることを目的に、沖ノ鳥島周辺海域の地球物理観測データの統合を行っています。通常の海洋調査では、対象となるフィールドを計画的かつ詳細に調査するのが一般的ですが、地球物理観測データの統合では、船が出航してから取得し続けたデータを集積し、一つにまとめる手法を採用しています。今回の研究調査では、JAMSTEC(海洋研究開発機構)が公開しているデータや産業技術総合研究所、その他の機関で蓄積された過去のデータを集め、それらを統合・整理しています。


A.海底下の構造を明らかにすることによって、沖ノ鳥島を形成する海山がどのように発達してきたのか、その詳細を知ることができると期待しています。沖ノ鳥島は九州・パラオ海嶺という海嶺の一部に位置していますが、この海嶺の形成過程自体は大枠で理解されています。伊豆・小笠原海嶺から離れ、九州・パラオ海嶺が形成され、その中で沖ノ鳥島の海山が発生したとされています。しかし、沖ノ鳥島を形成する海山が、どの段階で形成され、どのように発展していったのかという詳細はまだ不明です。今回の研究調査で、沖ノ鳥島形成史の詳細を明らかにしていきたいと考えています。
A.沖ノ鳥島について、多くの人は名前を知っているものの、どんな島か知っている人は少ないと思います。私自身、偶然にも研究のきっかけがあったことで、沖ノ鳥島について初めて深く調べました。また、今年度からこの研究調査が始まったことで、大学3年生の研究室配属時に、沖ノ鳥島に行ってみたい、興味があるという学生が増えました。このことから、沖ノ鳥島に関心を持つためには、適切なきっかけが大切であると改めて感じました。私は学生に向け、講義を通じて沖ノ鳥島の魅力を伝えていこうと思います。
東京都においても、ウェブサイトでの情報発信やPRイベントの開催など、沖ノ鳥島に興味関心を持ってもらうための取組を実施していると聞いています。沖ノ鳥島の維持保全や利活用という観点においても、関心を持つことが重要な第一歩だと感じています。そのため、もっと多くの人が沖ノ鳥島に触れ、その魅力や重要性に気づくことで、より多くの発見や学びが生まれると嬉しく思います。