
A.現在、葛西臨海水族園におりますが、入都時は東京都の農林水産担当として、伊豆大島や小笠原諸島の父島など各地で勤務しておりました。水産職のため、水や生きものに関わる動物園や水族館での仕事も増え、上野動物園、多摩動物公園などでの勤務を経て、葛西臨海水族園に至ります。2013(平成25)年に飼育展示課長として着任し、副園長を経て、2019(平成31)年から園長を務めております。

A.子どもの頃から生き物が好きで、水辺でよく遊んでいました。その影響もあり、大学では水産を学びました。生まれも育ちも東京なので、地元で自身の専門性が活かせる仕事に就きたいと思っており、その一つに東京都の水産の仕事があったので受けたのですが最初は落ちてしまって……。一度別の仕事に就きましたが、多くの人に役立つことがしたいという思いが強く、再挑戦した結果、二回目で合格しました。

A.葛西臨海水族園の起源をたどると、日本初の動物園である上野動物園の園内につくられた、同じく日本初の水族館施設「観魚室(うをのぞき)」までさかのぼります。上野動物園開園100周年記念の際に、水族館を発展的に展開しようということになり、1989(平成元)年、東京都江戸川区の葛西臨海公園内に葛西臨海水族園が設立されました。葛西臨海水族園は、日本最古の水族館の流れを汲む水族園と言えるかもしれません。
葛西臨海水族園には、いくつか他にはない特徴があります。その一つは、「世界七つの海」です。海には北極や南極といった極地の海から、大西洋や太平洋などいろいろな海洋の環境がありますが、そういったところの生き物を一堂に会して見ることができます。もう一つは、「海と人間の交流の場」です。海と言っても、都市に暮らす人にとっては遠くの存在かと思いますが、葛西臨海水族園に来ていただくことで、身近に感じ、親しみを持ってもらえればと思っています。
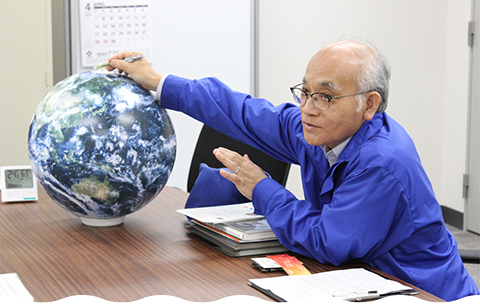
A.東京の海は広いのですが、中でも小笠原諸島やその近海の生き物はとてもユニークです。魚類のユウゼンや固有陸貝のマイマイ類など、多様な環境に固有の生き物が数多く生息しています。ただし、生息環境は厳しくなってきているため、生息地の外側でこれらの生き物を増やしていこうという取り組みを行っています。フィールド調査で生物の生活状況を確認し、許可を得て一部の生物を採取したのち、水槽で飼育・繁殖させるなど、他の都立動物園とも連携して取り組み、そのプロセスについても展示を通じて紹介するなどしています。様々な水槽の展示を通して東京の海について皆様にお伝えすることは、今後も続けていきたいと思いますし、伝え続けることに意味があると感じています。これも、東京にある水族館としての使命の一つだと思っています。
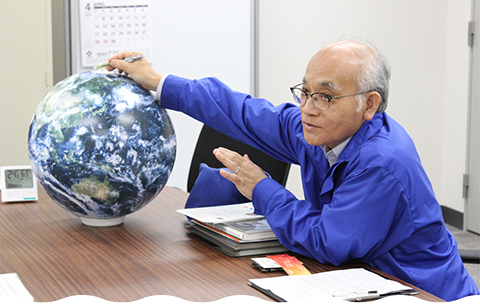

A.アオウミガメは寿命が長いので、卵を産み繁殖できるようになるまでは数十年かかると言われています。現在の施設ではずっと飼い続けることができないため、現地で繁殖した子ガメを預かって、水族園の施設で捕食されにくいサイズまで育てたのち、現地で標識をつけて放流します。ある程度の大きさに成長したウミガメは放流後、捕食されにくく十分に野生復帰できるだろうと考えられるため、このサイクルを繰り返し行っています。

A.まず、生き物を安全に輸送するためのパッキング(梱包)が重要です。種類や大きさに応じた適切なパッキングを行い、輸送中の環境を最適に保つことに細心の注意を払っています。また、酸素供給や温度管理も徹底する必要があります。必要な酸素量を確保し、温度を適切に保つために、それぞれの生き物に合わせて設定を行っています。さらに、必要に応じて移送時期や時間を意図的にずらすなど、生き物がストレスを感じないよう、様々な対策を講じています。
A.はい、あります。沖ノ鳥島と南鳥島に1回ずつ行きました。両島とも、現在の東京都の島しょ農林水産総合センター(小笠原水産センター)の研究員だった時に調査のために行っております。
A.沖ノ鳥島と南鳥島は交通手段が限られているため、行くまでが大変でした。船(東京都の調査船みやこ)を利用するのですが、まず大島から小笠原に行き、そこから約1000キロも進むため、途中で燃料を補給する必要があり、かなり時間がかかった記憶があります。当時の南鳥島には自衛隊と気象庁、海上保安庁の職員が常駐しており、中央には飛行機が着陸できる滑走路が一本あります。南鳥島は非常に暑かった印象があります。先輩職員たちは水中の調査を担当し、私は陸上の調査を担当したため、灼熱の砂浜で足の裏をやけどしそうになりました(笑)。
A.小さなお子さんも非常に関心を持ってくれて、ずっと見ている方もいらっしゃいました。特に沖ノ鳥島や南鳥島はあまり知られていない場所なので、まずは興味を持ってもらい、そこから情報を伝えていくことは有効だと感じました。もちろん、私たち水族園としては、実物をできるだけ見ていただきたいという気持ちがあります。しかし、このような手法でのPRも、まず理解してもらったり、関心を持ってもらったりするためのアプローチの一つだと感じました。
A.「東京の海」は日本最東端の南鳥島から最南端の沖ノ鳥島まで広大であり、とても多様性のある海だと思っています。東京の海に住む生き物たちがいかにバリエーション豊かで、どのように今暮らしているのかなど、いろいろと感じてもらえるような展示や取り組みを引き続き行っていきます。
A.水族園に来られる方の年齢層は幅広いため、プログラムを作成する際にはターゲットを絞っておりますが、まずは見てもらうことを重視しています。また発信に当たっては、自然の正しい情報をお伝えすることを基本としています。名前や学名などのほか、情報は限らざるを得ませんが、新しい情報を順次発信し、生き物に興味を持ってもらうことを目指しています。そのうえで、「こういうことを知ってもらいたい」といった追加情報も発信しています。この取組は水族園としての教育普及プログラムの一環であり、各年代の方に合わせた様々なプログラムを展開できるよう工夫しています。また、水族園に来られない方やこれから来ようと思っている方に向けて、ホームページやSNS(Xやインスタグラムなど)で情報を発信しています。YouTubeの専用チャンネルにも200以上の動画を投稿しており、学校の教材向けのものも公開しています。先生が学校の授業などで使いたい場合にも閲覧可能です。水族園は動物園よりも堅いイメージを持たれることもあるため、一生懸命工夫して情報発信に取り組んでいます。
A.現在、35周年を記念したレストランメニューをご提供しています。テーマは「これまでとこれから」で、一部のメニューはリバイバルとして、昔提供していた懐かしいメニューも復活させていきます。ご要望ボックスも設置しているので、リクエストしてもらえたら反映される……かもしれませんね(笑)。

A.葛西臨海水族園は2024(令和6)年で35周年を迎えます。世界中の生き物だけでなく、東京の生き物も展示し、昨年、累計来園者数が6000万人を超えるなど、多くの方々に来園いただいております。東京の町中にいると、なかなか感じることができないかもしれませんが、水族園に来ることで、沖ノ鳥島や南鳥島をはじめ、まだまだ知られていない東京の海を身近に感じていただけます。目で見て、耳で音を聞き、鼻で匂いを感じるなど、五感を通じて生き物の魅力を体験していただければと思います。
