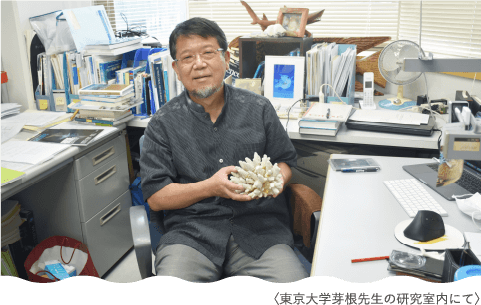
A.沖ノ鳥島は約40万㎢という広大な排他的経済水域を持ち、国土保全上非常に重要な島とされています。その水域内にある生物や鉱物などの資源を調査・開発できるとなれば、島の保全を図ることは当然のことでしょう。しかしそれだけが理由だと私は思いません。沖ノ鳥島と同じように、海面上昇による水没の危機に瀕している環礁小島嶼国家はたくさんあります。共通の課題を解決するために沖ノ鳥島で構築した技術を移転・連携していく。そういった視点で沖ノ鳥島を守っていくことが必要だと思います。
A.「東京大学海洋アライアンス沖ノ鳥島・小島嶼国研究会」で東京大学大学院工学系研究科の加藤教授にもお話しいただいたのですが、莫大な量のレアアース、海底資源が眠っていると聞きました。また、沖ノ鳥島は熱帯気候に属する日本の最南端の島であり、フィリピン海プレートの上に存在するため、地学・生態学から見ても非常に貴重な島だと思います。もちろん研究面においても、地質的・地形的特質や生物学的プロセスなど、様々な重要課題があります。
A.分かっていないことが多く、まだまだ研究・調査が必要です。沖ノ鳥島と言えば鉱物資源の開発や水産資源の利用などの話題が目立ちますが、私個人的には、環境保全や研究調査などのソフト面ももっと表に出した方がよいのではないかと思います。
アメリカやイギリス、フランスなど世界各国で、排他的経済水域を含む沖合域で大規模な海洋保護区((Marine Protected Area, MPA))の設定が進められています。例えばイギリスは、チャゴス諸島の周辺海域の海洋保護のために海洋保護区を設定しました。すなわち、環境保全の義務を果たすということを前面に出して資源の確保・権利を得ているのです。日本は、島の経済的利活用という視点が主で、環境保全、研究調査に関する働きかけがまだまだ弱い印象です。沖ノ鳥島とそれを取り巻く環境を守るという根本的な取り組みや研究調査こそ大切なのではないかと思います。
A.まだ研究調査が不十分で広く知られていないこともあり、沖ノ鳥島や南鳥島の環境や自然についての研究に取り組む学生は少ないですね。特に南鳥島は陸上生態系の研究の点からも課題が多いので、研究の幅も広がって面白いと思います。

A.南鳥島の最高標高はおおよそ9mもあり、なぜそこまでサンゴの礫が積み上げられたのか分かっていません。たとえ大規模な台風などが起きても、そこまで打ち上がるなんてよほどのこと。その形成メカニズムについては謎に包まれています。高海面時にサンゴ礁が作られてできたものが削り残されたのか、島の核にもっと古い時代のサンゴ礁があるのか、いろいろ考えられます。島の地質や形成過程、地質、サンゴの研究は私の専門分野なので、非常に興味深いです。
A.戦前の調査によると今より多く小島が満潮時にも姿を現していたことが記されており、なぜ北小島と東小島以外は消失してしまったのか分かっていません。以前、護岸されていない時に2つの島を確認したところ、キノコのような形をしていました。そこから推測すると、島は基部のサンゴ礁とつながる根付きである可能性が高いかもしれません。ですが、国際法上の島の定義はともかく、沖ノ鳥島全体としては東西4.5km、南北1.75kmのなす型をしたサンゴ礁を指しますね。

A.現在、沖ノ鳥島は温暖化に伴う海面上昇により水没の危機に瀕しています。島の維持にはサンゴ礁の形成過程が不可欠であり、私たちが取り組んでいる生態工学的創成技術を活用して島の保全を図らなくてはいけません。沖ノ鳥島の研究調査を基点に、その成果を同様に水没の危機にある環礁小島嶼国家にも適用できるよう取り組んでいきたいと思います。