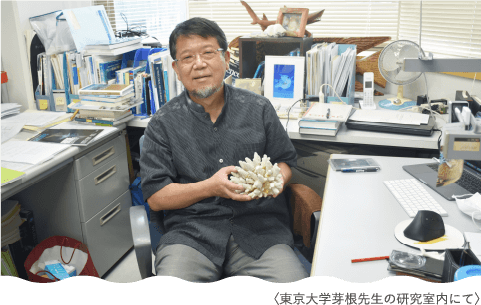
A.1回は那覇から、あと1回は小笠原から沖ノ鳥島を目指しました。いずれも船中2泊、現地は1日もしくは2日でした。沖ノ鳥島の全体は南北1.75km、東西4.5kmなのですが、満潮時には大半が海面下に沈んでしまい、国際法上の島と言えるのは北小島と東小島の2つのみ。どちらも人が寝そべられるくらいの大きさです。島はコンクリートの護岸で囲まれており、そこに上陸しました。

A.わずか1日なのでじっくりと調査はできなかったですが、それぞれの島がどのような状況下におかれているのかを確認しました。また周辺のサンゴがどのように生息しているのかということも調べました。調査はシュノーケルやスクーバで潜り、海の中の撮影も行いました。沖ノ鳥島の縁(礁嶺)は低潮位の時は干上がります。内側(浅礁湖)はもっとも深いところでも水深5mくらいですので、シュノーケルでも潜ることができるんですよ。
A.私が持ち帰ったのではないですが、保全事業のために国土交通省京浜河川事務所や水産庁が採取した沖ノ鳥島のサンゴは、東京大学総合研究博物館に寄贈されました。同様にサンゴ礁の岩塊も公開されています。島の周辺で採取された岩塊の硬度を測定するなど、工学的な視点から研究・調査し、その後に東京大学に寄贈していただいたので、現在は博物館の入口に展示されています。現在も岩塊にサンゴ骨格がみられますよ。
A.1回目と同じく、2回目も国交省の保全事業という目的で沖ノ鳥島に訪れました。調査というより島の様子を視察することが主な内容です。見た目はあまり変わらないのですが、水産庁が取り組んでいる沖ノ鳥島サンゴ種苗生産技術の開発調査によると、2014(平成26)年頃からサンゴが急激に白化などで減少しているようです。そういう意味では沖ノ鳥島は大きく変化しつつあると思います。

A.ひとつは先ほども述べましたが、水産庁が取り組んでいる沖ノ鳥島サンゴ種苗生産技術の開発です。増殖したサンゴの一部を折り取って移植し、成長させる、このことを「無性生殖」と言い一般的な研究で取り上げられるのですが、水産庁はサンゴを卵から孵化させて増やしていく「有性生殖」に取り組んでいます。環境状況が厳しい沖ノ鳥島のサンゴを増やして成長を助けようというものになりますね。私もこの開発が実施された2006(平成18)年から委員として参加させていただき、現在は委員長として苗生産技術の事業の評価に関わらせていただいています。
もうひとつは島の保全技術ですね。今ある島をただ護岸で守るだけではなく、より効果的に保全するにはどうすればよいか、またサンゴの断片を積み上げて島の水没を避けることはできないかなどを検討するプロジェクトが進められています。島をコンクリートで固めて嵩上げしても国際法上は島として認められないので、サンゴの礫が堆積して島を形成していくという自然のメカニズムを活用しなければいけません。そのために新たな生態工学技術を用いた研究に取り組んでいるのです。
また沖ノ鳥島で活動する船舶が円滑に係留、停泊できるよう港湾設備を建設しています。これにより可能となりうる様々な環境保全対策を現在議論しているところです。
さらに東京都は、水産や都民・国民に沖ノ鳥島のことを広報する事業を続けています。
まとめますと、沖ノ鳥島の保全事業に取り組んでいるのは水産庁、国交省、東京都ということになります。
A.そうですね。ただ水産庁はサンゴを増やしましょう、国交省は島を保全して利活用しましょう、と目的はそれぞれです。セクターを越えて総合的に沖ノ鳥島の保全を検討する「沖ノ鳥島勉強会」を2006(平成18)年に立ち上げ、お互いに情報交換ができる場をつくりました。現在は、東京大学海洋アライアンス沖ノ鳥島・小島嶼国研究会として、大学、研究機関、省庁、財団、民間の200名以上のメンバーが参加しています。ただサンゴを増やすだけではなく島を守るため、環境保全対策技術を構築して、環礁の島々に適用するグランドデザインを省庁とセクターをこえた皆さんで構築していきましょうというのが目的です。
A.今世紀中に海面上昇は最大1mにもなると言われています。現在の沖ノ鳥島の高さは数十センチなので海面上昇で水没してしまう可能性は非常に高いですね。水没の危機を避けるにはサンゴを成長させて、壊れた断片を積み上げて島を自然に維持させる。生き物の力で環礁の島が形成されるメカニズムを手助けしてあげているという感覚ですね。
A.はい。西表島にあるバラス島はサンゴの礫が積み上がることによって形成された陸地です。どのようなしくみで島になったのかを調査し、沖ノ鳥島の保全に役立てたいですね。また環礁の島の地形はどのようなメカニズムで形成されたのかを知ることも重要です。その調査を参考にして研究に励み、サンゴの力によって環礁の島の水没を防げるようにしたいです。
A.はい。現在1年で約3mm上昇しています。海面上昇は温暖化で水が膨張する熱膨張と氷河の融解が原因となります。IPCCの報告によると南極やグリーンランドなどの氷が溶けることにより、すでにもう0.2m海面上昇しており、今世紀末までにまたさらに0.1〜0.8m上昇すると予想されています。さらに温暖化で水温が上昇して、沖ノ鳥島でもしばしばサンゴの白化が大規模に起こっています。
海面上昇と水温上昇に耐えられるようにサンゴの増殖にもより力をいれていかないといけません。
A.人為的に島を高くすればよいという問題でなく、自然のメカニズムをうまく使って島を守らなければいけません。サンゴの成長を促し壊れた断片を島周辺に積み上げて島を形成していく。今までそのような技術はなかったので新しい生態工学エコロテクノロジーとして取り組んでいきたいです。沖ノ鳥島で構築したこの技術を、同様に海面上昇によって水没の危機にあるツバルやキリバス、モルジブなどの環礁の島々に適用することによって、太平洋の環境安全保障を主導することが、私たちプログラムの目標です。