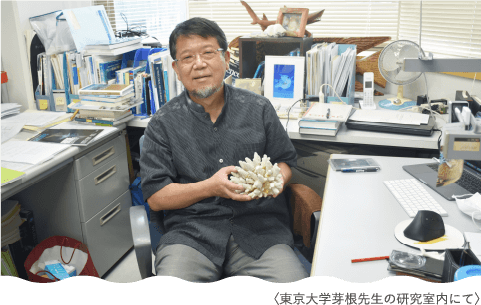
A.温暖化によるサンゴの白化や海洋酸性化によるサンゴの骨格形成の阻害、海面上昇による水没など、主に地球環境変化によってサンゴ礁がどのような影響を受けるのかということを研究しています。
A.18歳のときに大学のダイビングのサークル(海洋調査探検部)でサンゴ礁に興味を持つようになったのがきっかけです。実際に研究を始めたのは修士になった22歳のとき。私が研究をはじめた当時は、サンゴ礁に関する研究者は非常に少なかったのですが、次第に増えて現在はサンゴ礁学会に約600人の研究者がいます。私もサンゴ礁に魅せられてもう40年以上になりますね。
A.最初は琉球列島のサンゴ礁の調査を始めたのですが、その後にマリアナ諸島、パラオ共和国、ツバル、マーシャル諸島共和国など海外にまで研究対象を広げました。現地ではフィールド調査を行い、研究室に持って帰って採取試料の測定・分析に取り組んでいます。
A.私は理学系研究科(地球惑星科学専攻)の教員ですので、地球環境学・地球生態学・自然地理学・人間環境システム学、また地形地質調査法などの講義・実習を行っています。もちろん地球環境学や自然地理学という視点からサンゴやサンゴ礁を取り上げることもあります。昨年からオンラインによる講義が増えましたが、私たちの研究はどうしても対面による実習が必要です。感染防止に十分配慮しながら、学生と一緒に地形調査などに取り組んでいます。
A.これまでにサンゴ礁をテーマに研究したドクターを10人ほど輩出しました。現在研究室に学生はいませんが、特任研究員と支援職員が研究を進めています。今後、研究室で学位をとった研究者が、サンゴ礁のことをさらに解明してくれるだろうと期待しています。

A.サンゴ礁がリング状につながり、その内側に深さ数10mの浅い海を取り囲む地形を「環礁」と呼び、当初私はその研究に取り組んでいました。国土のほとんどが環礁だけからなるマーシャル諸島共和国やマジル、モルジブなどの標高は約1-2mしかなく、水没が危惧されていたため、2000(平成12)年前後から調査を始めたのですが、沖ノ鳥島も同様に水没の危機にあることがわかったのです。そこで、沖ノ鳥島の調査が、世界における環礁の保全にも還元されるのではないかということで、研究会を立ち上げました。沖ノ鳥島は孤立しているので、自然の生物作用だけでは海面上昇に対応した島の新たな形成は望めません。そのためサンゴなどの石灰化生物の生産力をあげてやることが必要不可欠なのです。私たちは造礁力の高いサンゴの移植や種苗生産、有孔虫の導入など、生態工学的な技術開発で沖ノ鳥島の維持に努めています。島ができる自然のプロセスをサポートできるよう日々研究に取り組んでいます。